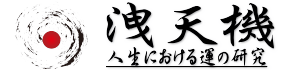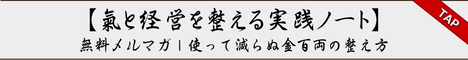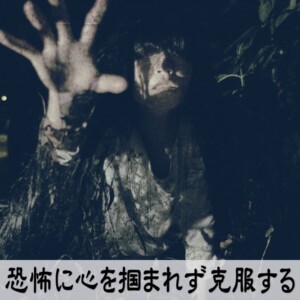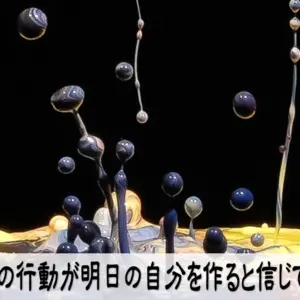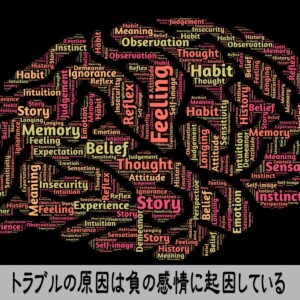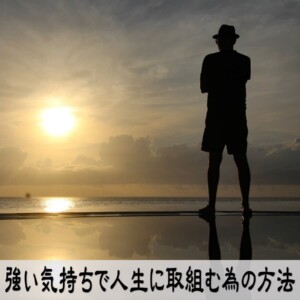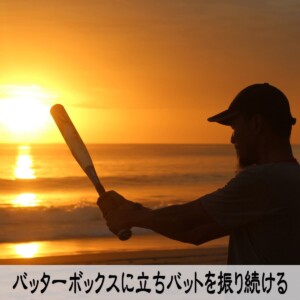多くを語るほど伝わらなくなるという言葉の不思議な仕組み

言葉は便利なようで伝わりにくいものであり、思いのすべてが相手に届くことはまずない。話せば話すほど理解は遠ざかり、言葉の重みも薄れていく。そもそも言葉は自分のためではなく、相手のためにあるもの。だからこそ、伝わらない前提でやさしく丁寧に話す姿勢が大切になる。多くを語るより、静かに向き合うことで心が通じることもある。伝える力とは、話す量ではなく伝え方に宿る。(内田游雲)
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトの「運の研究-洩天機-」は、運をテーマにしている。他にも、この世界の法則や社会の仕組みを理解しスモールビジネスの経営を考える「気の経営」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。
「えっ、それはそんな意味じゃなかった」
そう思ったことがあるはずだ。
言った本人に悪気はないのに、相手の顔が曇ることは日常的にある。よかれと思って話したのに、なぜか空気が重くなる。そんな経験は、誰にでもある。
ちゃんと話したのに伝わらない
毎日、言葉で誰かとやり取りしている。相手も自分も同じ日本語を使っているのに、なぜこんなに伝わらないのか。気を遣っているつもりでも、伝わり方は思ったよりズレる。言葉とは、思ったより不器用な道具なのだ。
たとえば、自分の顔を言葉で説明してみる。「ちょっとつり目で、鼻は小さめで、唇は薄い」――そう言ったところで、相手の頭に浮かぶ顔はバラバラだ。何度も鏡で見てきた自分の顔ですら正確に説明できない。そんな言葉で、他人の気持ちをぴったりと動かそうとすること自体が、無理のある話である。
頭の中で思っていることを100とすれば、言葉にできるのはせいぜい80。聞いた相手が理解するのはその70%程度。さらにそれを誰かに伝えようとすると、また精度が落ちる。部長から課長、課長から部下へと話が伝わると、最終的に3割しか残らない。これは伝言ゲームではなく、現実である。
たとえば「この服どう思う?」と聞いて「いいと思うよ」と返されたとする。「何がどういいの?」と思ってしまうこともあるだろう。会話は成立しているようで、実はズレている。そんなすれ違いは、日常の中にたくさん転がっている。
だからこそ、「どうして伝わらないのか」と怒るより、「そもそも伝わらないのが普通」と考えてみる。そうすれば、言葉の使い方が少しだけやさしくなる。重くなりすぎず、笑いも交えながら伝えることができるようになる。
言葉は、万能ではない。伝えきれない前提で向き合うほうが、心が軽くなる。
言葉は3割しか届いてないらしい
「ちゃんと説明したつもりなのに、なんで伝わってないの?」
そう感じたことがある人は多いだろう。けれど、それはあなただけの問題ではない。言葉というもの自体が、そもそもあまり伝わらないものだからだ。
たとえば、頭の中で思っていることが100あるとする。それを言葉にできるのは、せいぜい80くらいだと言われている。そこから相手が理解できるのは、さらにその70%程度。つまり、自分の思いが100%あるとして、相手に伝わるのは最大でも56%。それでもまだ良い方で、そこからまた誰かに伝えようとすれば、3割しか残らない計算になる。
部長が課長に話し、それを課長が部下に伝えるような場面では、「伝わっている気がする」が「実は3割しか届いていない」という現象がよく起きている。会社の伝達ミスや認識のズレは、たいていこの構造から生まれている。
日常の会話でも同じことが言える。「あのときのあれ、こういう意味だったんだよ」と後から説明する場面は、まさに言葉がうまく届いていなかった証拠だ。「そんなつもりじゃなかった」と言いたくなるけれど、実は最初から伝わっていなかった可能性が高い。
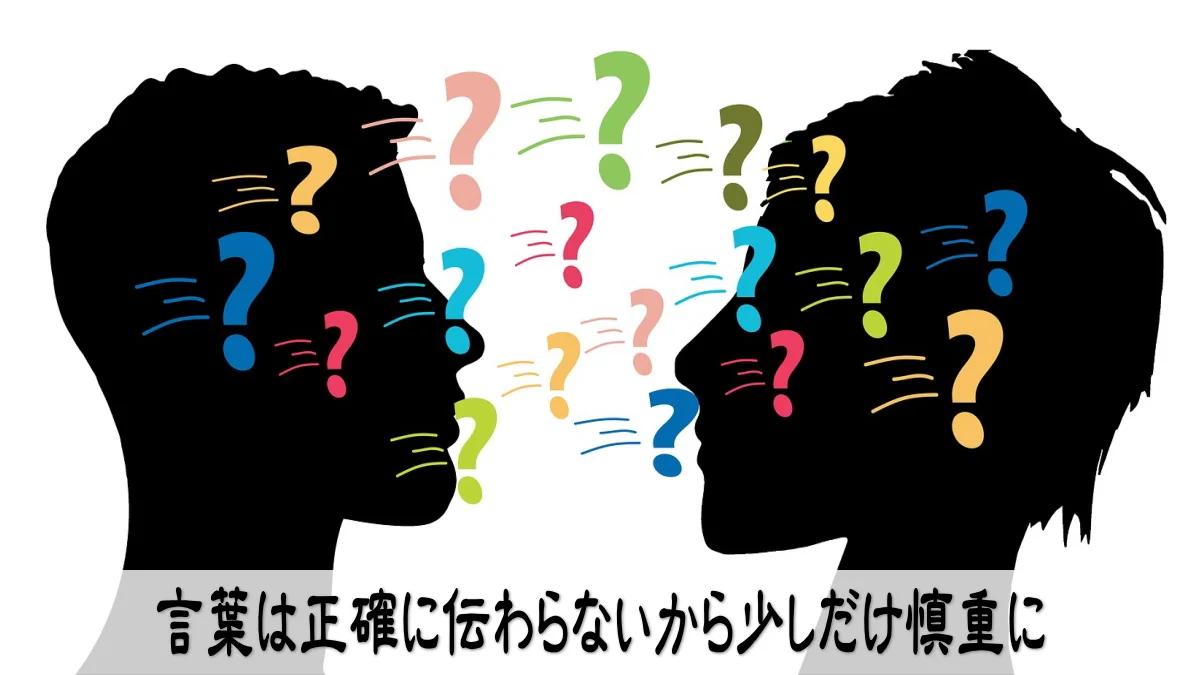
それでも人は、伝わらないとわかると、もっと言葉を重ねようとする。語彙を増やし、例え話を加え、丁寧に話すようになる。でもその努力が、逆に伝わりにくくしてしまうこともある。説明が長くなると、相手はだんだん話を聞かなくなる。内容を覚えていられなくなる。そして話している人に対して「なんだか軽い」と感じるようになる。
本当は、たくさん話すことが信頼につながるわけではない。むしろ、短く、的確に、そして相手の理解を信じて預けるように話すほうが、伝わる確率は上がる。
言葉は正確に伝わらない。だからこそ、伝えるときには少しだけ慎重になってみる。伝わって当然、ではなく、伝わらない前提で。すると、言葉の選び方が自然と変わってくる。
言葉はじぶんのためじゃない
言葉は、自分の思いを伝えるもの。そう思っている人が多い。でも実は、言葉は自分のためではなく、相手のためにある。そう考えると、コミュニケーションの景色がガラッと変わってくる。
たとえば、誰かに話しかけるとき。ほとんどの人は「自分が言いたいことを言っている」だけになっている。自分の不満、自分の意見、自分の正しさ。もちろん、それが悪いわけではない。ただ、言葉は出た瞬間に自分のものではなくなる。相手の耳に届いた時点で、それはもう「相手の世界」に入っている。
自分の中でぐるぐるしているうちは、言葉は内側のものであり、誰にも影響を与えない。でも、一言でも口にした瞬間、それは外に出ていく。自分の感情のゴミ出しではなく、誰かの心に届くプレゼントとして投げられる。そのことを忘れてしまうと、言葉はとたんに乱暴なものになる。
たとえば「つい本音を言っちゃって・・・」という言い訳。これはよくあるけれど、そもそも本音は黙っていれば無害でいられる。口に出すという行為は、相手の感情を揺らすことでもある。だからこそ、本音であれ何であれ、発するなら「どう届くか」を想像する必要がある。
そしてもうひとつ。言葉は出すだけでなく、受け取ってもらって初めて成立するという点も大きい。つまり、言葉はキャッチボール。相手が受け取りやすいように投げることが大切だ。スピードも角度も、相手の状況によって調整する必要がある。自分だけが気持ちよく話していても、それが相手にとってノイズになってしまっては、本末転倒である。
言葉は、相手のためにある。そう思って話すと、自然と声のトーンや選ぶ言葉が変わる。柔らかくなり、温度が下がり、空気が和らぐ。そこに、コミュニケーションの本当の意味がある。
しゃべりすぎると軽く見られる
たくさん話せばわかってもらえる。言葉を尽くせば、気持ちは伝わる。そう信じている人は多い。けれど実際は、話せば話すほど、相手の理解は遠ざかっていくこともある。
なぜかというと、人は聞けば聞くほど、情報をどんどん忘れていく。話が長くなるほど、覚えているのは最後の一言くらい。まして、話し手が力んでいればいるほど、聞く側の頭はだんだんオフになる。人の集中力は意外と短く、心の中では「またこの話か」と思っていることもある。
よかれと思って説明を重ねるうちに、話はくどくなり、重くなり、かえって誤解を深める。誤解を解こうとして出した言葉が、さらに火に油を注ぐこともある。頭のいい人ほど、表現を変えて何度も伝えようとするが、それが逆効果になることも少なくない。
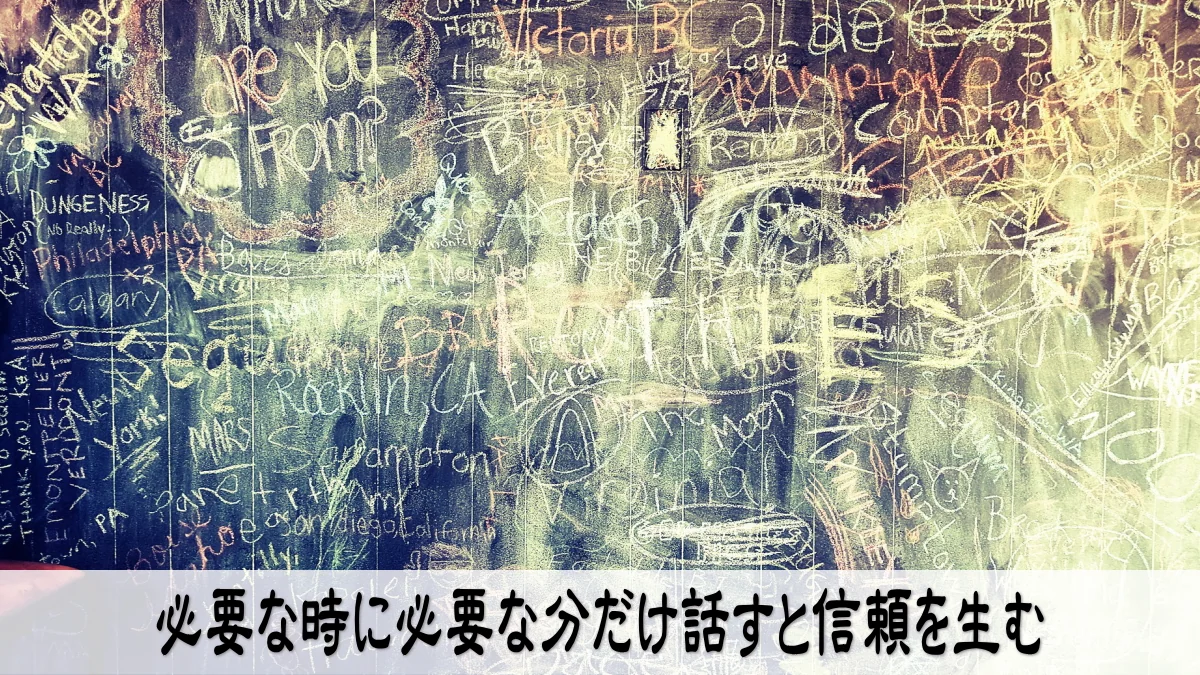
さらに、人は多弁な人に対して「軽い」という印象を持ちやすい。どれだけ深い内容でも、言葉が多くなればなるほど、言葉そのものの重みが薄くなる。大切なことをポンポンと話してしまうと、「この人、なんでも軽く話すな」と思われてしまうことがある。
だからこそ、必要なときにだけ、必要な分だけ話す。これが意外と信頼を生む。静かにしている人ほど、何かを言ったときに「おっ」と注目されるものだ。沈黙には力がある。言葉に重みを持たせたいなら、話さない時間を味方につけた方がいい。
古来より伝わる学問に、「黙養」という科目がある。
「1日黙して、一語も語らず。
3ヶ月黙して、一語も漏らさず。
3年黙して、一語も発せず」
つまり、話さない訓練だ。
言葉は、出すことばかりが大事なのではない。話すことを学ぶとは、実は話さないことを学ぶということなのだ。
言葉は伝わらない前提で丁度いい
言葉は伝わらないもの。そう割り切ってしまうと、かえって気持ちがラクになる。そもそも、完璧に伝えることが目的ではない。大切なのは、伝えようとする姿勢と、伝わらなかったときの柔軟さだ。
たとえば、相手に思いがうまく届かなかったとき。「なんでわかってくれないの」と苛立つより、「伝える努力がまだ足りなかったかな」と一歩引いてみる。その一歩があるだけで、関係はずいぶん優しいものになる。伝わらなさを前提にすれば、言葉の温度も自然と落ち着く。
また、伝えたい内容があるときほど、言葉をたくさん使いたくなるものだ。だけど、前の章で見たように、多弁は逆効果になることが多い。だからこそ、「これは全部は伝わらないだろう」と思っておくとちょうどいい。むしろその方が、聞き手のペースに合わせて言葉を整えることができる。
そして、言葉は意味だけでなく、「伝わろうとする気配」そのものに力がある。たとえば、ぎこちなくても、一生懸命伝えようとしてくれる人の話は、なぜかちゃんと届く。うまくまとめた言葉より、心のこもったつたない一言の方が伝わることもある。だからこそ、完璧に伝えることよりも、相手の立場に立って「どんなふうに受け取るだろう」と想像することの方が、よっぽど大切だ。
言葉は伝わらない。それでも伝えたいことがあるとき、人は自然にやさしくなる。だから、伝わらないことを怖がらずに、ちょっと肩の力を抜いてみるといい。気持ちを全部わかってもらおうとしなくていい。わかろうとしてくれた、その姿勢だけで、すでに気持ちは届いている。
言葉は、全部が伝わらない。でも、全部伝わらなくても、人はつながる。だからこそ、言葉の「足りなさ」を前提に、ゆっくりと、やさしく、丁寧に話していくこと。それが、ほんとうのコミュニケーションであり、運を拓く小さな習慣なのだ。